「自分たちのアイデンティティに貢献したい」「LUCY ALTER DESIGN」が届ける新しい日本茶文化とは

デザイン会社でありながら、日本茶専門店として、実店舗・EC・サブスクリプションという三位一体のサービスを展開し、国内外の数々のデザイン賞を獲得してきた、「LUCY ALTER DESIGN」。
どうして日本茶に着目した事業を展開しようと思ったのか、またどういった世界観を提供していこうとされているのか、代表取締役社長の青柳様と、取締役の谷本様にお話を伺ってきました。
(取材は6月にオンライン上で行いました。)
インタビュイーのご紹介
- 青柳智士様(代表取締役社長・クリエイティブディレクター・デザイナー・サムネイル左側)
- 谷本幹人様(取締役・クリエイティブディレクター・デザイナー・サムネイル右側)
日本茶の体験価値とブランド理解を最大化する。
本日はインタビューにご協力いただきありがとうございます。まず、貴社が展開しているサービスの全体像を教えて下さい。
―青柳様
僕たちには嗜好品飲料であるお茶を提供する者として、お客様一人一人の体験価値とブランド理解を最大化するために、より良い接点を持つことが求められています。
そのために、創業当初から実店舗、オンラインストア、サブスクリプションの三角形をバランス良く拡大していくことを念頭において事業を推進しています。
その中でも貴社のサブスクリプションサービスである「TOKYO TEA JOURNAL」はその中でもどういった役割ですか?
―青柳様
その三角形の1つとして、より良い接点の構築の役割を担っています。
月に1回、これまでお客様が飲んだことがない2種類の茶葉と情報誌をお届けします。
情報誌だけではわからない茶園の様子などは、QRコードや、煎茶堂東京公式Youtubeから映像で御覧いただけます。
取り扱う茶葉は全て単一農園・単一品種の一番茶のみです。
月額500円(別途配送料300円)でシングルオリジンならではの個性やストーリーを楽しんでいただいています。
―谷本様
3つの事業が提供する価値には2つあります。
我々からお客様に対するご提案の全てをお客様の好みやこれまでのご利用状況に応じて変化させる「最適化」と、お茶や日本文化に関してお客様が未知の情報を知ることができるという「セレンディピティ」です。
サブスクリプション事業はそのどちらにも欠かすことができません。

アイデンティティである日本文化に対して貢献したかった
まさに「三位一体」ということですね。どうしてデザイン会社であるのに日本茶事業を始めようと思われたのですか?
―青柳様
「LUCY ALTER DESIGN」はデザイン会社として今もお客様に貢献させていただいていますが、そういった事業の中で見えてきた、お茶の消費課題、生産・流通課題にデザイン会社としてアプローチすることで解決につなげることができるのではないかというのが、始まりですね。
僕の中で消費者の方々の動きが変わっていくんじゃないかという確信めいた思いもありました。
―谷本様
僕たちはやはり日本文化の中で生まれ育ってきているので、そういったアイデンティティと呼べるものに何らかの貢献ができないかと思ったんです。
伝統的な日本文化に対して、現代のデザインを活かすとなると、一筋縄でいかないこともあったのではないですか?
―青柳様
そうですね。簡単なことはほとんどありませんでした。
ふたりとももともとデザインをやっていたので、実店舗を立ち上げたりすることは当然やったことはなかったですから、挑戦の連続でした。
―谷本様
そういう時、お客様からの声はとても励みになっています。
僕らが提供しているお茶は少し高い分、ギフトとしても利用してもらえることが多いんです。
そういうときに、少しだけプレミアムな体験を作り出せているのかなと実感しますね。

生活を少しでもカラフルにできるような体験を届ける
体験という言葉がありましたが、サービス全体を通じてどういったCX(顧客体験)を作り出したいですか?
―青柳様
日本茶という総合芸術の一部を、断片的にでも取り入れていただき、生活を少しでもカラフルにできるような体験を提供できたらいいなと思っています。
日本茶を知らなかった方たちに対してそういったものを一つでも提供できれば、消費者の方々にとっても、生産者の方々にとっても、日本にとっても、良いことと言えるのではないかと思っています。
―谷本様
また先進国ほど、物質的な豊かさが必ずしも幸福度に直結していないと思います。
我々の売っている茶葉ってスーパーで売っている茶葉と比べてもちろん高くなってしまうのですが、その高さの背景にあるストーリーに共感してもらい、少し特別な何かを体験していただきたいと思っています。
現状そのためにどういったことに取り組まれていますか?
―青柳様
それはやはり、先ほども谷本の方から申し上げた三位一体のサービス展開による、「最適化」と「セレンディピティ」のご提供ですね。
弊社のストアでサブスクリプションユーザーは会員割引15%が全てに適用されるなど、使用すればするほどメリットを享受できるような形になっています。
こうした遠隔でのレシピ提供や茶葉のレコメンドを自信を持って行うために、私たちは自社開発した「急須」と「シングルオリジン(単一農園・単一品種)の茶葉」を提供しています。


シングルオリジンにこだわる理由は何ですか?
―青柳様
シンプルに非常に美味しいというのももちろんあるんですが、それだけではありません。
特定の量を特定の温度で入れる、ちゃんとしたレシピで入れるというのは、知らない人が多い。
今ペットボトルでお茶が流通していて普段から飲まれる方も多いと思うんですが、これはお茶を入れて楽しむということが全く想定されていないんですね。
私たちが届けたいのは「お茶を楽しむ時間」です。
茶葉が開いていく様子をしっかりと見て、お茶が入っていく様子を楽しむ。
そのために「透明急須」というものも作りましたし、そのプレゼンテーションのために銀座にシングルオリジン煎茶専門店、三軒茶屋にハンドドリップ専門店も作らせていただきました。


お客様同士の有機的な繋がりを強めていく
今後はどういったことに取り組んでいきたいですか。
―谷本様
日本茶という伝統的でリアルな文化なので、もっと店舗や口頭で良さを伝えていきたいと思います。
オンライン上ではやはり限界もありますし、三位一体であるからこそできる、事業展開を強めて行きたいですね。
デザイン会社としての海外での経験も、海外展開では活かして行きたいと思っています。
―青柳様
これまでは、弊社とお客様という1対1の繋がりだったものを、参加型のコミュニティ化させることにより、より有機的なシナプスの結合に近い顧客基盤とエンゲージメントを構築していきたいと考えています。
そのためのクラウドファンディングやオンラインイベントの開催を行いノウハウを貯めています。
少しでも日本茶という総合芸術の魅力を、ひとりひとりが取り入れていくことで、生活の奥行きの創出や、生産者の方々の地位向上に貢献していきたいと思います。

編集後記
デザインというバックグラウンドを活かして、日本茶という日本人のアイデンティティとも言える文化のアップデートを試みる、「LUCY ALTER DESIGN」の青柳様と谷本様にお話を伺いました。
実店舗、オンラインストア、サブスクリプションという3つの事業があって初めて実現できるCXは、消費者の方々、生産者の方々、そして「LUCY ALTER DESIGN」の方々という、三方にとって最適な事業展開を促進していくことでしょう。
本文中では紹介しきれなかったものの、下記も展開されている。

参考:梅体験専門店「蝶矢」
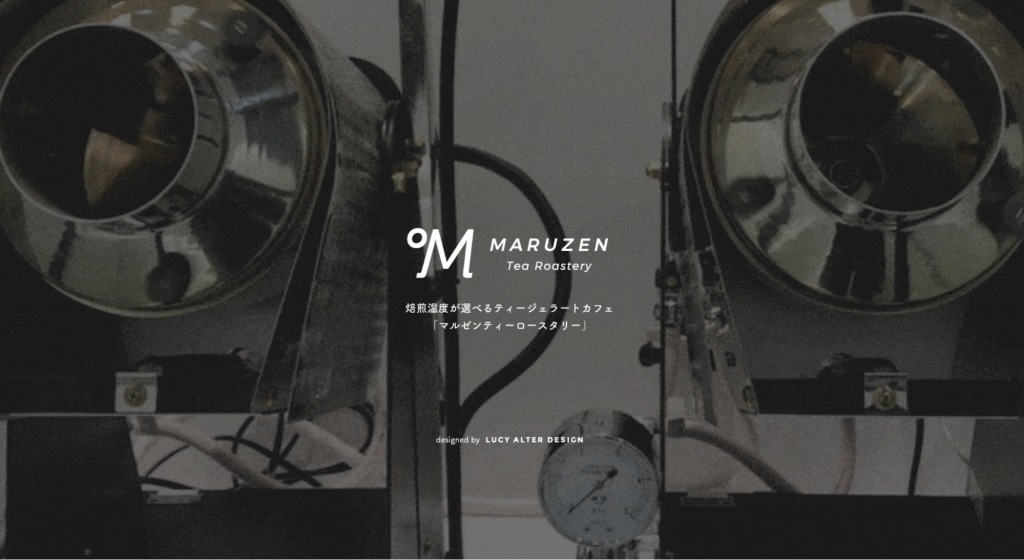
参考:ティージェラートカフェ「Maruzen Tea Roastery」

参考:バリスタ常駐型社内カフェ導入支援サービス「Garden」
青柳様、谷本様、お忙しい中インタビューにご協力いただきありがとうございました。
-
前の記事
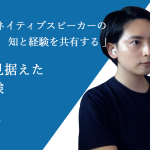
「世界中のネイティブスピーカーの知と経験を共有する 」Lang-8の世界を見据えた顧客体験 2020.07.16
-
次の記事

「すれ違い」を恋のきっかけに。ユーザーを飽きさせないCROSSMEのCX戦略とは 2020.07.21
